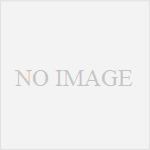注意: この記事は1年以上前に掲載されたものです。情報が古い場合がありますのでお気を付け下さい。
1月7日は、七草とも呼ばれ、この日に七草粥を食べて、あるいは正月気分が抜ける人も多いだろう。ここではそんな七草についていろいろ書いてみたい。
七草は元々は人日の節句で、古代中国の風習が日本に伝わって、形を変えつつも定着したと言われている。
さて、七草というと、今日では春の七草のことを連想する人が多いが、元々は七草は秋の七草を指していて、春の七草は「七種」と書いていたそうである。
春の七草
- セリ
- ナズナ
- ゴギョウ(ハハコグサ)
- ハコベラ(コハコベ)
- ホトケノザ(コオニタビラコ)
- スズナ(カブ)
- スズシロ(ダイコン)
秋の七草
- オミナエシ
- オバナ(ススキ)
- キキョウ
- ナデシコ(カワラナデシコ)
- フジバカマ
- クズ
- ハギ
七種粥を食べる風習は古代中国で行われていた七草を羹にして食べる風習が変化したものと言われており、その風習は平安時代に始まり、江戸時代に一般に広まったそうである。
しばしば「伝統」を持ち上げる人を見かけるが、それが果たして真の意味での伝統なのか、甚だ疑問を抱かざるを得ないことが多いが、あまり気づかないところで伝統が生きているところもあるということなのだろうか。