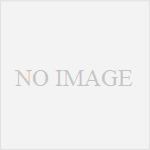はじめに
塩は人間の生命活動にとって不可欠な存在である。ナトリウムは細胞の浸透圧調整や神経伝達、筋肉の収縮などに関与し、日々の食生活においても欠かすことのできない基本的な調味料として利用されてきた。
しかしながら、20世紀後半以降、塩の摂取量が高血圧や心疾患、脳卒中といった生活習慣病のリスク因子として注目されるようになり、「減塩」が公衆衛生上の重要課題として浮上した。
とりわけ日本においては、味噌・漬物・醤油など塩分を多く含む伝統食が日常に根付いており、諸外国と比較しても塩分摂取量が高い傾向にある。そのため、厚生労働省をはじめとする行政機関や食品業界が一体となって、減塩政策や低ナトリウム食品の開発に取り組む動きが活発化している。
一方で、「塩はすべて悪者なのか」「天然塩は精製塩より健康に良いのか」といった疑問も根強い。本稿では、減塩が推奨されるようになった背景を整理し、日本と海外における減塩政策の違いを概観した上で、塩の種類と健康への影響についても科学的知見を踏まえて検討する。
1. 減塩が推奨されるようになった背景
塩分の過剰摂取が健康に及ぼす影響については、20世紀中盤以降、医学・疫学の進展により明らかにされてきた。中でも注目されてきたのが、高血圧との関連である。ナトリウムの摂取が過剰であると、血管内の水分量が増加し、それに伴って血圧が上昇する仕組みがある。この関係は複数の大規模調査により実証されており、塩分制限が血圧を下げる効果を持つことは、現在では国際的にも広く認識されている。
特に日本は、高血圧による脳卒中の死亡率がかつて極めて高かった国の一つである。厚生労働省が発表する「国民健康・栄養調査」によれば、1970年代には1日あたり平均で13〜14gもの食塩を摂取していたとされる。これは世界保健機関(WHOの推奨基準)の約3倍にあたる水準である。
このような背景から、日本では1980年代以降、医療機関や保健所などを中心に減塩指導が強化され、学校教育や保健指導の現場でも「減塩」が一つの標語として定着していくこととなった。1990年代以降は、即席食品や外食産業にも減塩の波が広がり、食品メーカー各社が「減塩しょうゆ」「減塩みそ」などの製品を相次いで投入するに至った。
なお、減塩の推奨には個人差や例外も存在する。汗を多くかく労働者や高温環境下にある人々、あるいは特定の腎疾患を持つ患者などにとっては、塩分の制限が必ずしも有益とは限らない。そのため、画一的な塩分制限ではなく、個々人の生活環境や健康状態に応じた指導が必要である点にも留意すべきである。
2. 日本と海外における塩の摂取状況と政策
2-1. 日本の現状
日本においては、塩分摂取量の多さが長年にわたり健康課題として指摘されてきた。2022年の「国民健康・栄養調査」によれば、成人男性の1日平均食塩摂取量は約10.9g、女性は9.3gであり、いずれもWHOの推奨上限である5gを大きく上回っている。この背景には、日本の食文化が深く関与している。
伝統的な和食は、味噌汁、漬物、醤油など、保存性と旨味を高めるために塩分を多く含む調味料を使用する料理が多い。これらは長い歴史の中で育まれてきた食文化の重要な構成要素である一方、ナトリウム摂取量の過剰という現代的な問題を抱える要因ともなっている。
こうした状況に対し、行政と民間企業は段階的な対策を講じてきた。厚生労働省は健康日本21(第二次)において、2023年度までに成人の平均摂取量を男性8.0g、女性7.0gにまで引き下げる目標を掲げた。また、食品メーカー各社は、減塩を前提とした調味料や加工食品を開発・販売しており、「減塩しょうゆ」「減塩みそ」などが一般消費者に広く受け入れられつつある。
さらに、コンビニエンスストアや飲食チェーンなどでも塩分量を明記したメニューが増加しており、消費者の選択を後押しする環境整備も進んでいる。ただし、外食や中食に依存する生活スタイルでは、依然として「見えない塩分」の摂取リスクが残されている点には注意が必要である。
2-2. 海外の事例
フィンランドでは、1970年代に心血管疾患による死亡率が世界でも最も高い水準にあったことを背景に、国家主導で減塩キャンペーンが展開された。同国では食品に対してナトリウム含有量の表示義務化が行われ、さらに「高ナトリウム食品」には警告ラベルを貼付する制度も導入された。その結果、塩分摂取量は30年以上にわたって段階的に減少し、心疾患と脳卒中による死亡率も大幅に低下した。
イギリスにおいても、2000年代初頭から公衆衛生庁(NHS)と食品業界が協力し、食品の塩分基準を設けて自主的な削減を促進した。これにより、パンやスープ、加工肉製品などの塩分量が減少し、国民全体の摂取量も10年で約15%減少する成果を上げている。
アメリカでは、FDA(食品医薬品局)が加工食品に含まれるナトリウムの基準値設定に取り組んでおり、外食産業にもガイドラインを提示している。ただし、州や企業による対応にはばらつきがあり、国全体としては依然として高い摂取傾向が続いている。
これらの事例は、減塩政策が単なる個人努力ではなく、制度的な支援や食品業界との連携によってこそ実効性を持つことを示している。日本においても今後、こうした先行事例を参考にしながら、社会全体での取り組みとして減塩を進めていくことが求められる。
3. 塩の種類と健康への影響:精製塩 vs 天然塩
3-1. 精製塩と天然塩の定義
塩と一口に言っても、その製法や成分によってさまざまな種類が存在する。中でも最も広く流通しているのが「精製塩」であり、これは工業的に生産された塩化ナトリウム(NaCl)99%以上の高純度な塩である。日本ではイオン交換膜法などにより海水中のナトリウムを抽出・再結晶化することで大量生産されており、価格も安価で、安定した品質が特徴である。
一方、「天然塩」とは、天日干しや釜焚きなどの自然な工程で得られた塩を指す。これには海水を原料とする海塩のほか、地中から採掘される岩塩なども含まれる。天然塩にはマグネシウム、カルシウム、カリウムといった微量ミネラルが自然のまま含まれており、その風味や溶け方にも個性があるとされる。
3-2. 味と用途の違い
味覚の面から見ても、精製塩と天然塩には一定の違いがある。精製塩は純度が高いため、塩味が直線的で鋭い印象を与える。一方、天然塩は含まれるミネラルの影響により、やや丸みを帯びた風味やまろやかさを感じやすく、素材の味を引き立てる用途にも適しているとされる。
3-3. 健康と安全性の違いはあるのか?
しばしば「天然塩は健康に良く、精製塩は体に悪い」といった言説が見られるが、科学的な観点から見れば、こうした単純な二項対立は正確ではない。実際のところ、健康に対する影響は塩の種類よりも摂取量の多寡が主たる要因である。
天然塩に含まれるミネラル(例:マグネシウム、カリウム)は、生理的に重要な役割を果たす栄養素であり、不足すれば筋肉痙攣や高血圧などのリスクが高まることもある。しかし、塩を通じてこれらのミネラルを摂取する場合、摂取できる量はごく微量にとどまり、栄養補給源としての寄与は限定的である。
3-4. 医学的観点からのまとめ
医学的に見た場合、減塩の基本的な目的はナトリウムの過剰摂取を防ぐことであり、塩の種類は本質的な問題ではない。たとえ天然塩であっても大量に摂取すればナトリウムの過剰に変わりはなく、むしろ「天然だから安全」との思い込みが過剰摂取を助長する危険すらある。
4. 減塩と伝統文化の両立は可能か
日本の伝統的な食文化において、塩は単なる調味料ではなく、保存性の確保や発酵の促進といった実用的な役割を担ってきた。味噌、醤油、漬物、梅干し、干物といった食品は、いずれも塩を多用することにより保存期間を延ばし、風味を深める工夫が施されている。
しかしながら、現代社会においては冷蔵・冷凍技術や物流網の発達により、保存のために高濃度の塩を用いる必要性は薄れてきている。そのため、伝統食品の製造方法や味付けを見直し、塩分を抑えた形で提供する試みが進んでいる。
5. まとめ:賢く塩とつきあうには
塩は人間の生命活動にとって不可欠であり、同時に過剰摂取による健康リスクも抱える、いわば「必要だが、取り扱いには注意が必要な」存在である。そのため、塩とのつきあい方には一律の正解があるわけではなく、個人の健康状態、生活環境、食文化に応じた柔軟な姿勢が求められる。
今後は、「見えない塩(hidden salt)」への意識を高めると同時に、出汁や香味野菜など、塩分に依存しない旨味や風味の引き出し方を学ぶことが、健康と味覚の両立への鍵となるだろう。