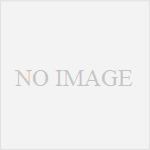はじめに:なぜ、資産運用が必要なのか
「銀行に預けておけば安心」――そんな言葉がかつての常識だった。しかし、いまやそれは過去の話である。低金利が続くこの時代、預金だけではお金は増えず、むしろ物価上昇によって価値が目減りすることさえある。
私たちの世代にとっては、金利が高かった時代を知らないのが普通だ。物心ついたときから預金金利は年0.001%程度。お金は眠らせておくだけで増えるものではない。だからこそ、若いうちから「お金に働いてもらう」感覚を持つことが大切になる。
資産運用とは、一部の裕福な人やギャンブラーだけのものではない。むしろ、将来の安心を自分で築くための、実践的な生活戦略である。収入が限られる若いうちこそ、「時間」という最大の武器を使って、資産を育てていくことができる。
本記事では、新社会人が無理なく始められる資産運用の基本と、着実な第一歩の踏み出し方を解説する。
資産運用における三本の柱
1. 「貯金」と「運用」は役割が違う
「お金を貯める」と一口に言っても、そこには性質の異なる2つの方法がある。
一つは、すぐに使えるように手元に置いておく貯金。もう一つは、将来に備えて育てていく資産運用。
どちらも必要であり、重要なのは役割の切り分けである。急な出費や生活費には貯金で備え、老後や長期の目標には運用で備える。目的をはっきりさせることが第一歩だ。
2. 複利の力を味方につける
複利とは、「利息にさらに利息がつく仕組み」のこと。 たとえば、毎月1万円を年5%で20年間運用すると、元本240万円に対して最終的な資産は約412万円になる。
この力は、短期間では大きく感じないかもしれないが、時間が経つほど効果を発揮する。だからこそ、若いうちから少額でも運用を始めることが重要になる。
3. リスクとリターンはセットである
「リスクがあるから投資は怖い」――そう思う人もいるかもしれない。しかし、リスクとは「振れ幅」であり、危険という意味だけではない。
リターンが大きいものはリスクも大きい。逆にリスクが小さいものはリターンも小さい。重要なのは、自分がどこまでのリスクに耐えられるかを知ること。そして、それに応じて資産の配分を決めることだ。
最初にやるべきことは「守る仕組み」づくり
資産運用を始めるうえで、最初に取り組むべきは「いざという時の備え」を整えることである。運用に夢中になってすべてのお金を投資に回してしまうと、突発的な出費に対応できず、生活が不安定になるおそれがある。
そこで必要なのが「生活防衛資金」である。これは、病気やケガ、失業など、収入が一時的に途絶えたときや急な支出に備えるための現金であり、運用資金とは切り離して確保しておくべきものである。
どれくらい用意すべきか?
一般的には、「生活費の3〜6か月分」が目安とされる。たとえば、月の生活費が15万円なら、最低でも45万円、できれば90万円程度は現金で確保しておきたい。個人事業主や転職予定の人など、不安定な状況にある場合は、より多めに用意しておくと安心だ。
どこに置いておくべきか?
生活防衛資金は、すぐに引き出せる安全な場所に保管することが基本である。具体的には、以下のような選択肢がある:
- 普通預金口座(流動性重視)
- 定期預金(使いにくさを利用して手を出しにくくする)
- 積立定期預金(毎月自動で積み立てる仕組み)
中でも「積立定期預金」は、給与天引きや自動引き落としに設定すれば、強制力をもって貯蓄を習慣化できるためおすすめである。
上限設定で“資産の滞留”を防ぐ
生活防衛資金は必要不可欠だが、過剰に貯めすぎると“眠ったままの資産”になってしまう。 そこで、「生活費の6か月分まで」といった上限をあらかじめ決めておき、それを超える分は投資に回すというルールを設けるとよい。このようにしておけば、「守るお金」と「育てるお金」のバランスを保ちつつ、資産形成もスムーズに進められる。
守りの仕組みこそ、継続の基盤
投資はあくまで余裕資金で行うもの。守るべき現金を確保しているからこそ、値動きに一喜一憂せず、腰を据えて長期投資に向き合うことができる。「いざという時も慌てなくて済む」安心感こそが、投資を継続するための土台となるのだ。
初心者におすすめの制度と投資方法
新NISA(少額投資非課税制度)
2024年からスタートした新NISAは、投資によって得られた利益に税金がかからない制度であり、つみたて投資枠(年間120万円)と成長投資枠(年間240万円)がある。
つみたて投資枠は、あらかじめ認定された長期投資向けの投資信託しか買えないが、その分安心感がある。毎月自動で積み立てる設定にして、全世界株式型(オルカン)などを選ぶのが王道だ。
成長投資枠はETFや個別株も対象になるため、余裕資金のスポット購入などで使うのが現実的である。
iDeCo(個人型確定拠出年金)
iDeCoは老後資金のための制度で、原則60歳まで引き出せないが、掛金は全額所得控除される。
長期投資に向いているため、最初から株式中心で運用して問題ない。オルカンが選べるなら1本で十分。なければ「除く日本」90〜95%、「日本株(TOPIXなど)」5〜10%で近い構成を作れる。
インデックス投資
NISAやiDeCoで実際に買う商品は、インデックスファンドが基本になる。
「無配当・再投資型」を選ぶことで、分配金による課税を回避し、非課税の恩恵を最大限に活かすことができる。
どれくらい投資すればいいのか?
投資を始めるときに最も悩みやすいのが、「毎月いくら投資すればいいのか?」という点である。結論から言えば、最初から完璧な額を設定する必要はない。大切なのは、無理なく続けられる金額からスタートすることである。
基本の目安:手取り収入の5〜10%
一般的には、手取り収入の5〜10%を目安にするとよい。たとえば、手取りが月20万円であれば、1万〜2万円を目標とするのが無理のない水準だ。
最低限のスタートライン:月5,000円
iDeCoでは月5,000円から始められる。これは制度上の最低額でもあるが、最初の一歩としてはちょうどよい。また、新NISAでは、証券会社によっては月100円からでも投資信託の積立が可能である。つまり、始めようと思えば、学生アルバイトの収入でも無理なく投資は始められる。
先取り・固定費化が鍵
「余ったら投資する」という考え方では、結局投資に回す余裕は生まれにくい。むしろ、家賃や通信費と同じように「先に投資額を確保する」方が確実である。給与日に自動積立が引き落とされる設定にすれば、習慣化もしやすい。
ライフステージや変化に応じて調整する
投資額はずっと一定である必要はない。結婚や転職、子育てなど、ライフステージが変化すれば、収入や支出も変わる。それに応じて、投資額も柔軟に見直してよい。むしろ、「月〇円」と固執せず、その時々の状況に合った金額で続けていく姿勢が長期的な成功を生む。
ボーナスや昇給をチャンスに変える
ボーナス時には、特別積立のように一部を追加投資に回すのも良い戦略である。たとえばボーナスのうち10〜20%を成長投資枠でスポット購入に使うなど、非課税枠の活用に幅を持たせられる。
また、昇給したタイミングで積立額を千円単位で引き上げていくことで、無理なく資産形成を強化できる。
絶対に避けたい「やってはいけないこと」
資産運用で成功するためには、やるべきことを知るだけでなく、「やってはいけないこと」を明確に理解しておく必要がある。これらの落とし穴は、初心者だけでなく経験者でも陥りがちなものばかりであり、資産形成の妨げになるだけでなく、精神的なダメージも伴うことがある。
1. 借金をして投資をする
投資は余裕資金で行うのが原則である。クレジットカードのリボ払いやカードローンを使って投資を行うことは、損失が出たときに借金だけが残る「二重苦」に陥る危険性がある。レバレッジ型投資も同様で、リスクを取るにしても、それが背伸びしたものであってはならない。
2. 短期的に大儲けを狙う
仮想通貨、FX、未公開株といった投資対象は、大きく儲かる可能性がある一方で、大きく損をするリスクも伴う。資産運用の基本は長期・分散・積立である。一発逆転を狙う行動は、往々にして資産形成を台無しにする。
3. SNSやインフルエンサーの情報に振り回される
SNSでは華々しい成功談ばかりが目立ちやすく、損失や失敗は語られにくい。フォロワー数が多いからといって信頼できるとは限らない。投資判断は、制度や商品の仕組み、リスクなどを自分の頭で理解して行うべきである。
4. 他人の投資法をそのまま真似する
人にはそれぞれ収入、家族構成、将来の目標、リスク許容度がある。誰かが成功した方法でも、自分にとって最適とは限らない。まずは自分の目的と状況に合った方針を立てることが先決である。
5. 怪しい情報商材や副業に手を出す
「月利10%保証」「簡単に儲かる」「自動で資産が増える」――このような甘い言葉には要注意。高額な情報商材や、実態のない副業スキームに引っかかると、資産を失うだけでなく信用情報にも傷がつく場合がある。金融庁登録の有無、販売元の正体、返金保証の実態などを冷静に確認したい。
6. 相場が下がったときに慌てて売る
資産運用をしていれば、必ず値下がりの場面に出会う。そんなときに感情に任せて売却してしまうのは「狼狽売り」と呼ばれ、最も損失を拡大させやすい行動である。逆に、定期積立をしている人にとっては「安く買えるチャンス」でもある。相場の変動に一喜一憂せず、長期的視点で続けることが重要だ。
7. 損切りできずに塩漬けにしてしまう
「そのうち戻るだろう」と根拠なく保有し続け、結果的に身動きが取れなくなるケースは少なくない。特にテーマ型や個別株に偏った投資では、冷静な見直しが求められる。出口戦略(いつ、なぜ売るのか)を最初から考えておくことが、後悔の少ない投資につながる。
おわりに:未来は「習慣」で変わる
資産運用とは、短期間で大きく儲けるためのギャンブルではなく、日々の積み重ねによって未来をよりよくするための生活習慣である。
月々の小さな積立、収支の見直し、制度の活用――これらは一つひとつは地味だが、続けることで確かな差を生み出す。習慣とは、最初の一歩がすべてだ。そして一度始めれば、それは自分の生活に組み込まれ、やがて“当たり前”になる。
未来の自分が、「あのとき始めておいてよかった」と思えるようにするために、今この瞬間にできることがある。それは、生活防衛資金を確保し、証券口座を開設し、月5,000円でも良いから投資を始めてみることだ。
続けるうちに、自分に合ったスタイルが見えてくる。不安は減り、自信が生まれる。そして何より、経済的な自由と選択肢が手に入りやすくなる。
次回は、「NISA・iDeCo・課税口座をどう使い分ける?実践ガイド編」として、制度をどう使い分けるか、年齢や目的に応じた実践的な運用戦略を紹介していく予定である。
焦らず、惑わされず、地道に、そして確実に。未来を変えるのは、今日という一日の行動からである。