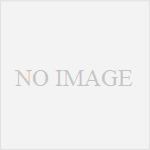前回のGNU/Linuxディストリビューションを選ぶ — 2025年編(1)ではDebian/Ubuntu系とRed Hat系を中心にディストリビューションについて説明を行った。今回は前回の記事では説明できていなかったディストリビューションを中心に説明をしていきたい。
GNU/Linuxディストリビューション選び(2)
Debian/Ubuntu系
Linux Mint
Linux Mintは、2006年にUbuntuから派生して登場したディストリビューションで、直近のDistroWatchのページヒットランキングでは2008年頃からトップクラスを位置するほど知名度の高いディストリビューションになっている。
多くのディストリビューションではデスクトップ環境にGNOMEをメインに採用しているのとは違い、Linux MintはCinnamonやMATE、Xfceなど比較的軽量なデスクトップ環境を搭載しており、UbuntuやRHELなどの主要なディストリビューションと比較すると比較的貧弱なマシンパワーの環境でも快適に動くことがあると言われている。
Linux Mintの特徴として、mintToolsと呼ばれるソフトウェア群を有しており、ソフトウェアの管理やWiFi設定、バックアップなどのソフトウェアが豊富にある。
DebianやUbuntu向けの情報を活用することができるので、デスクトップ環境の違いを考えれば初心者でも比較的使いやすいディストリビューションといえるだろう。
MX Linux
MX Linuxは、比較的軽量なDebian GNU/Linux派生のディストリビューションである。MX LinuxもXfceやFluxbox、KDEをデフォルトのUIとして用いており、比較的マシンパワーを必要としないと言われている。
MX Linuxの特徴として、MXツールと呼ばれるユーザー向けのツール群が整備されており、設定系やメンテナンス系などを一元的に扱うことができる特徴がある。
全体的には旧来のGNU/Linuxらしさを残すインターフェースであり、どこか懐かしくも感じるデザインになっているのが特徴である。
Red Hat系
AlmaLinux
AlmaLinuxは、The AlmaLinux OS Foundationが開発しているディストリビューションで、CentOS Linuxの終了を受けてその後継となるディストリビューションを提供する目的でCloudLinux社が開発開始したディストリビューションである。
Red Hat社の方針転換の影響を受けたディストリビューションのひとつであり、登場当初はRHELとソースコードレベルで互換性を確保する方針だったが、2023年半ば以降はバイナリーレベルでの互換性を維持する目標に方針転換が行われた。
リリースサイクルおよびサポート期間は基本的にRHELに準拠する方針となっており、従来のCentOS Linuxの代替として利用するには概ね問題ないレベルと言われている。
Rocky Linux
Rocky LinuxはAlmaLinuxと同様にCentOS Linuxの終了を受けてその後継を目指して開発・頒布されるディストリビューションで、Rocky Enterprise Software Foundationが開発・頒布をおこなっている。プロジェクト立ち上げにはThe CentOS Projectの初代創設者Gregory Kurtzer氏が関わっており、ディストリビューション名は共同創設者のRocky McGaugh氏に因む。
Red Hat社の方針転換の影響を受けたディストリビューションのひとつで、2023年半ばのRed Hatのソースコード公開制限の対応を非難し、プロジェクトの主要スポンサーCIQ、オラクル、SUSEの三社で「OpenELA」を設立、RHEL互換ディストリビューションの開発を表明した。
CentOS Linuxの終了に伴って発足したAlmaLinuxとRocky Linuxは今後も差別化が進む見通しとなっていると考えられている。
Arch系
Arch系はArch Linuxに始まるディストリビューションの系統で、Pacmanによるパッケージ管理システムと、多くの派生ディストリビューションでローリングリリースモデルを採用していることが大きな特徴である。
ベースとなっているArch Linux自体は敷居の高い部類のディストリビューションだが、派生ディストリビューションは初心者でも扱いやすいものも少なくない。
主に以下のディストリビューションがこの系統に属する。
openSUSE / SUSE Linux Enterprise
openSUSEはopenSUSEプロジェクトにより開発が行われているディストリビューションで、SUSEより開発が行われていた「SUSE Linux」からノベルによる買収でコミュニティーベースでの開発に移行する際に現在の名称に変更された。
SUSE Linux Enterpriseは、openSUSEの成果を元に商用向けに販売されているディストリビューションで、企業での利用に強みを持っている。
openSUSE/SUSE Linux EnterpriseはYaSTによるテキストまたはグラフィックベースの管理ツールを搭載しており、ソフトウェアの管理やネットワークの設定、ユーザーの設定などをYaSTで一元的に管理を行うことができる。