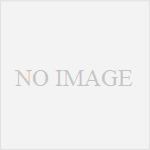第1章:熊本県での馬インフルエンザと殺処分の誤解
熊本県での発生は、国内での確認としては2008年以来17年ぶりであり、TBSやFNN、朝日新聞などが報じている(TBS/FNN/朝日新聞)。発症した馬は隔離され、症状の治癒を待つという対応が取られている。しかし一部のSNSやコメント欄では、「感染した馬は殺処分されるのではないか」といった内容の投稿が散見された。
結論から言えば、馬インフルエンザは殺処分の対象とはならない。 このような誤解が広まる背景には、他の家畜伝染病や人間社会でのパンデミックへの過敏な反応があると考えられる。本稿では、馬インフルエンザの正しい知識と、馬における感染症の分類および対応方針の違いを整理し、「殺処分の必要がある感染症」と「そうではない感染症」との線引きを明確にしたい。
第2章:馬インフルエンザの正しい理解
馬インフルエンザ(Equine Influenza)は、インフルエンザウイルスA型(主にH3N8型)によって引き起こされる馬の急性呼吸器疾患である。感染力が非常に高く、短期間で多数の馬に広がる可能性があるが、致死性は低く、通常の飼育管理下においては死に至ることはまれである。
発症すると発熱(39~41度)、咳、鼻汁、元気消失などの症状が現れるが、通常2週間程度で回復する。人間への感染例は報告されておらず、人獣共通感染症としての懸念もない。
致死率は通常1%未満とされ、健康な馬であれば回復が見込める。ただし、免疫を持たない集団や若齢馬・高齢馬では重篤化リスクが上がる。2007年のモンゴルでの集団感染では、一部で致死率20~30%に達した例もあるが、これは極端な例である(NCBI文献)。
日本では「届出伝染病」に分類されており、獣医師が行政に報告する義務はあるが、殺処分は求められていない。 隔離、移動制限、ワクチン追加接種などの対応で拡大は抑えられる(農水省資料)。
また、日本国内では殺処分や安楽死に至った事例は確認されておらず、海外でも重篤な症例を除き安楽死は例外的措置にとどまる。
第3章:馬における殺処分対象の感染症とは
家畜伝染病予防法では、家畜に感染する疾病を「法定伝染病」「届出伝染病」「監視伝染病」に分類している。このうち殺処分の法的根拠があるのは法定伝染病に限られる。
馬が対象となる法定伝染病には以下がある:
- 京都府獣医師会)。
- 馬炭疽:炭疽菌による急性敗血症で、人獣共通感染症でもある。非常に稀だが、発生時は殺処分が行われる。
- ブルセラ病(状況依存):主に牛豚が対象だが、馬でも例外的に感染例あり。殺処分対応は感染状況により異なる。
これらと比較しても、馬インフルエンザは致死性が低く、管理可能な疾病であり、制度上も殺処分は不要とされている。
第4章:誤解が社会にもたらす影響と、正しい情報発信の重要性
「馬インフルエンザ=殺処分」という誤解がもたらす社会的影響は軽視できない。畜産業や競馬業界への風評被害、情報混乱、必要な防疫措置への理解不足などが生じうる。
また、SNSや一部メディアでセンセーショナルに拡散される情報は、科学的根拠よりも感情的な印象を優先させることがある。その結果、専門的対応が不当に非難される事態も起こりうる。
こうした中で、冷静かつ正確な情報発信の重要性は高まっている。感染症の法的位置づけ、実態、予防体制などを踏まえた広報が、社会のリスク認識と行動に大きな影響を与える。
参考までに、情報の信頼性に関する調査研究として、総務省の報告書も一読の価値がある。
第5章:おわりに──冷静な理解と対応を社会全体で
馬インフルエンザは管理可能な感染症であり、殺処分の対象にはあたらない。 名称や印象に引きずられて誤った理解が広まらないよう、制度・医学的な実態に即した冷静な対応が求められる。
社会的なパニックや誤情報の拡散を防ぐためには、正しい知識に基づいた行動が必要である。本稿がその一助となれば幸いである。