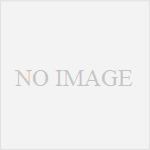はじめに
ChatGPTの登場以降、ブログ執筆のワークフローに変革が訪れている。だが、「全部AI任せで文章ができる」という期待と現実には乖離がある。筆者自身も、ブログ記事においては「こういうのを書きたい」「この切り口が面白そう」といった着想や構成はあくまで自分で行い、その上で、情報調査や表現の洗練においてChatGPTを積極的に活用している。本記事ではその具体的な活用法を紹介する。
着想と構成は“人間の仕事”
記事の核となる「何を書くか」「どう展開するか」は、依然として人間の得意領域である。読者が求める情報、どんな切り口が響くか、自分自身の経験や知識──これらは検索やAIでは出てこない「一次情報」である。
構成をChatGPTに提案させることも可能だが、盲目的に従うのではなく、自分の目的に照らして取捨選択する必要がある。AIは補助であり、構成の主導権は常に書き手が持つべきである。
調査・情報整理はChatGPTが得意な仕事
筆者が特に重宝しているのが、ChatGPTによる調査・情報整理のスピードと要約力である。以下に代表的な活用例を挙げる:
- 定義の明確化:「○○とは何か」を平易に説明
- 比較表の作成:「AとBの違いを表で整理して」
- 歴史的背景の把握:「○○はいつから始まったか?」
- 関連キーワードの収集:「○○に関する関連トピックを挙げて」
これにより、筆者は検索エンジンを何十ページも開く手間から解放され、企画や構成に集中できる。
ChatGPTの使いどころ(実例つき)
例1:知らない分野の基礎知識を得る
プロンプト例:「エッジコンピューティングについて初心者向けに300文字で説明して」
例2:比較表の作成
プロンプト例:「Markdown形式で、iDeCoと新NISAの違いを表にまとめて」
例3:冗長な説明を簡潔に言い換え
プロンプト例:「次の文を200文字以内に自然な『である調』に要約して:〜〜」
例4:構成の見直し
プロンプト例:「以下のH2・H3構成を論理的に改善して:…」
ChatGPTに任せすぎないための注意点
AIが出力する情報は、一見正しそうに見えても事実誤認を含む可能性がある。以下の点には特に注意が必要である:
- 数字・統計・法制度などは必ず信頼できる出典で裏を取る
- 自分の体験や思考を入れないと、ありきたりな記事になる
- 読者との共感・信頼を得るには“自分の声”が必要
おすすめの使い方Tips
- 指示は具体的に:「概要を教えて」より「○○について、初心者にもわかるよう200字で」
- 口調を指定する:「です・ます調」「である調」「論文調」など明示すると出力の質が上がる
- やり取りを蓄積してチューニングする:何度か繰り返すことで文体も自分に寄せられる
おわりに
ChatGPTは“代筆者”ではなく“参謀”として活用するのが本質である。書きたいテーマがあるなら、自分で構成を考え、その構成に必要な素材をChatGPTに整えてもらう──このスタイルならば、AIの力を引き出しつつ、オリジナリティも失わない。
文章を書くことは、考えることそのものである。だからこそ、思考の部分は自分の手に、情報の整備はAIに。二者の役割分担がうまくできたとき、ブログは飛躍的に進化する。