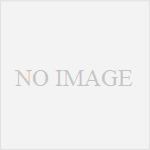近年では、企業での開発でも第三者が公開している自由なソフトウェアあるいはライブラリを使っているケースが増えている。しかしながら、それを巡ってトラブルの原因となるケースも増えている。
自由なのソフトウェア及びライブラリでは著作権は放棄されておらず ((例外としてパブリックドメインのものがある)) 、あくまで一定の条件に従えば自由に使ってよいというものである。最もこの「一定の条件」というものがクセモノなのだが。
自由なソフトウェアのライセンスとしてはBSD系 ((BSDライセンスやMITライセンス、Apacheライセンスなどを含む)) 及びGNU系 ((GPLやLGPLなど)) などがあげられる。
BSD系では基本的に「このソフトウェア及びライブラリを使うにあたって一切の保障はしない」「このソフトウェア及びライブラリを使っている旨を特定の場所に表示する」という条件が立てられている。一部では特許権に絡む条項、あるいは宣伝条項が付け加えられている場合がある。
GPL系では「このソフトウェア及びライブラリを使うにあたって一切の保障はしない」「このソフトウェア及びライブラリを使っている旨を特定の場所に表示するの他、さらに「このソフトウェア及びライブラリから派生する著作物もまたこのライセンスで使えるようにしなければならない」という趣旨の条件が加えられている ((不特定多数に公開する場合のみ、特定のメンバーでのみ利用する場合は公開不要である。BSD系も概ね同様のはず。)) 。
これらのライセンスについては、ライセンス上矛盾しないのであれば組み込むことは可能なのだが、矛盾した場合は組み込めない場合がある。また、企業用途ではリバースエンジニアリングを禁止する場合が極めて多く、その場合はGNU系のライセンスで公開されているものは利用できないことになる ((GNU系で比較的制限の緩いLGPLでもリバースエンジニアリングを許可しなければならないため)) 。BSD系であれば自己責任と著作権表記その他の条件を満たせばそのような制限がかからないため、リバースエンジニアリング禁止でも問題なく利用可能である。
開発で自由なソフトウェア及びライブラリを使うのであれば、それによるトラブルを未然に防ぐために、ライセンスには気をつけよう。
ウェブマスター。本ブログでITを中心にいろいろな情報や意見などを提供しています。主にスマートフォン向けアプリやウェブアプリの開発を携わっています。ご用の方はコメントかコンタクトフォームにて。