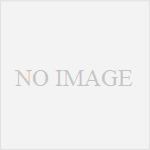2024年はCentOS Linux 7の完全サポート終了に伴い、Red Hat Enterprise LinuxのクローンとしてのCent OSが完全に終わり、Fedoraの開発成果をRed Hat Enterprise Linuxへ繋げるためのCentOS Streamに完全移行が完了した。近年はRed Hat社がRed Hat Enterprise Linuxのソースコード一般公開停止、ソースコードにアクセスする場合はクローンOS開発禁止を要請しており、この行為が「自由ソフトウェア」の理念に反するとしてオラクルやCiQ(Rocky Linuxの開発企業)等から非難があがっている。
さて、今回は今まで何度か掲載していたGNU/Linuxディストリビューション選びの記事の2025年版を目論んで記載した。今日主流となっているGNU/Linuxシステムを中心に記載してみたい。今回は主にDebian/Ubuntu系とRed Hat系から挙げてみた。
GNU/Linuxディストリビューション選び (1)
Debian/Ubuntu系
まず、Debian/Ubuntu系から記載したい。Debian/Ubuntu系は、Debianプロジェクトが提供している「Debian GNU/Linux」にルーツを置くディストリビューションで、そこからカノニカル社が派生して提供している「Ubuntu」が特にGNU/Linuxディストリビューションの中では主流の位置に立つことから、 このページでは便宜的に「Debian/Ubuntu系」と呼称している。
Debian/Ubuntu系の特徴は、パッケージ管理システムに「deb」形式を用いていることで、基本的にソフトウェアをインストールするときはディストリビューション公式のリポジトリや外部のリポジトリを参照して、コマンドラインやGUIフロントエンドを使ってインストールを行える特徴がある。あるパッケージをインストールするときはそれに伴って必要となるパッケージも自動的にインストールが行われる。
全体的には幅広いユーザーを対象にしている傾向にあり、初心者でも比較的使いやすい特徴にある。
Ubuntu
Ubuntuは、 前述の通り、カノニカル社が提供しているディストリビューションで、後述の「Debian GNU/Linux」派生のディストリビューションである。
利用用途に応じて、主にデスクトップ向け、サーバー向け、組み込み機器向けに特化したインストールメディアがあり、ユーザーは目的に応じて使い分けることができる。
サポート期間は9か月の通常版と、5年間のLTS版があり、頻繁にOSをアップグレードするのでなければLTS版を使うことが望ましい。特にサーバー用途では長時間稼働し続けることと、頻繁にパッケージを更新するわけではないため、長期のサポート期間が必要になるためである。
デスクトップ用途ではLiveメディアを使ってインストール前に試しに使ってみることができる。インストールもウィザードに従えば簡単にインストールできるようになっているのが特徴。
近年はマイクロソフト社との提携が進んでいて、Windows Subsystem for Linux(WSL)のデフォルトディストリビューションとして選ばれたり、クライアントHyper-VでもWindowsに並んでクイックインストールの有力候補に挙げられているといった、GNU/Linuxディストリビューションの中でも最も主流なディストリビューションとして挙げられている。
これに伴い、GNU/Linuxを扱うサイトでも情報が非常に豊富であるため、初心者が選ぶディストリビューションとしては最もおすすめできる。
Debian GNU/Linux
Debian GNU/Linuxは、Debianプロジェクトが提供しているディストリビューションで、Ubuntuの元となった。コミュニティー主導で開発が行われていて、プロジェクトとして進める上で掲げた「Debian社会契約」と呼ばれる独自のポリシーに基づいて開発が行われている。
Ubuntuの派生元となったディストリビューションで、Debian由来の機能の多くがUbuntuに引き継がれているといえる。一方でUbuntuは初心者向けを考慮してインターフェース面で多くの調整が行われているのに対し、Debianは比較的シンプルな状態になっているなどの違いがあり、初心者でもインストールしやすいように徹底されているUbuntuと比較すると、Debianはユーザーがある程度の知識を持っていることを前提に選択肢を提供する傾向にあるといった差異が見られる。
ウェブの情報量も豊富で、Ubuntuをメインに扱っている情報でもOSの系譜から応用が利く場合が多いため、ある程度の知識を持っていればUbuntuと並んでおすすめできるディストリビューションである。
Red Hat系
Red Hat系は、かつてRed Hat社が提供していた「Red Hat Linux」に起源を持つディストリビューションの系統で、今日では商用ディストリビューションの「Red Hat Enterprise Linux」およびそこから派生したディストリビューションが使われており、「CentOS Linux」がかつては根強い人気を持っていた。
パッケージ管理システムには「rpm」形式が用いられており、内部処理にかなりの違いはあるが、大まかにDebian/Ubuntu系のようにコマンドラインやGUIでパッケージ管理を行える特徴がある。
Red Hat Enterprise Linux
Red Hat Enterprise Linux (RHEL)は、商用用途で使われているディストリビューションの一つで、日本市場においては商用のディストリビューションのおよそ80%を占めているといわれている。多くのディストリビューションでは無償で提供されているが、RHELは有償のサブスクリプションライセンスを購入するのが原則となっている。個人開発者向けに特例として16台まで無償で利用可能なサブスクリプションがあるので、条件はあるものの無償で利用することはできる。
商用だけあってサポートは充実しており、OSのリリースから10年間のサポート期間があり、サブスクリプションに応じてRed Hat社からのサポートを受けることもできる。
一般利用者が導入するにはライセンスの関係から敷居の高いディストリビューションだが、商用ディストリビューションでは主流であることから、今後GNU/Linuxシステムを使った作業を行う上では候補に挙がるといえる。
インストールはAnacondaインストーラーが導入されており、インストールするために必要な設定が最初から一覧化されていて、必要な箇所を変更する方法でインストールを行える。
CentOS Stream
CentOS Streamは、CentOSプロジェクトが提供しているディストリビューションで、実質的に前述のRHELの先行試験版の立ち位置に当たる。かつてはRHELのクローンとしてのCentOS Linuxがあったが、それとは対照的の立ち位置といえる。
基本的にはRHELに近いものとして扱うことができるが、LinuxカーネルやGUIなどのソフトウェア群は新しいバージョンとなっており、最新版のCentOS Streamでは既存バージョンのRHELとの互換性が犠牲になっている場合があること、ローリングリリースの観点からバージョンを固定できない点から、完全なRHELのクローンとして使うことはできない。
サポート期間はリリースから5年と、Ubuntu LTS版に匹敵する。
後述のFedoraと比較すると長期利用はしやすいものの、バージョン固定を求められる使い方には向かないため、本番環境には向かないといえる。
Fedora
Fedoraは、Fedora Projectにより配布されているディストリビューションで、最新のソフトウェアを積極的に導入することで知られている。RHELにとっては開発版に相当し、Fedoraでの成果がCentOS Streamに引き継がれてRHELのリリース前の試験が行われて、 その成果をもとにRHELがリリースされる流れのうちの最初の段階に相当するといわれている。
半年ごとにメジャーアップデートリリースが行われる特性上、サポート期間は短く、今日ではおよそリリースから13か月でサポートが終了する。
新しい技術を積極的に導入するのであればおすすめできるディストリビューションである一方、一つのバージョンを固定するような使い方には全く向かないといった、向き不向きがはっきりしたディストリビューションといえる。